
「朝ドラあんぱん第68話」は、戦後の街で必死に生きる人々の声を伝えようと奮闘するのぶの取材が照らす子どもたちの声や、編集部での葛藤と仲間の支え、一県一夕刊の壁と新聞人の誇りなど、胸を打つテーマが盛り込まれています。絶望の隣は希望やの意味とは何かを、柳井嵩と万年筆のプレゼント、辛島健太郎の友情と成長、蘭子の夢と家族の支えを通じて丁寧に描き、朝田家の姉妹が語る未来、そして戦後の街と若者たちの小さな一歩がどのように希望へと繋がるのかを追いかけます。
- 戦後の街でのぶが子どもたちの声をどう取材したか
- 編集部の葛藤と仲間たちの支え合いの様子
- 一県一夕刊の規制と新聞人の誇りの意味
- 柳井嵩や健太郎、蘭子たち若者の小さな希望
朝ドラあんぱん第68話 希望と夢の物語

のぶの取材が照らす子どもたちの声
第68話で朝田のぶが取材したのは、戦後の街角で必死に生きる孤児たちでした。
のぶはチョコレートを配りながら子どもたちに声をかけ、「この街はどうなってほしい?」と問いかけます。
「元に戻ってほしい」「暖かい布団で寝たい」「お父さんを返してほしい」――小さな声には、戦争で奪われた日常と家族への切実な願いがにじんでいました。
この取材は、のぶが「子供らの声や顔を忘れんうちに書いちゅこうと思って」と語るように、
一つひとつの言葉を丁寧に記録しようとする記者としての真っ直ぐな姿勢を示しています。
また、のぶの視線は、ただの同情ではなく、子どもたち自身の夢を社会に伝えたいという使命感へと繋がっています。
子どもたちの声が編集部の大人たちにどんな影響を与えるのか――
のぶの原稿は、戦後の街と人々の心にわずかでも希望の光をもたらす“灯”になっていきます。
編集部での葛藤と仲間の支え
子どもたちの声を必死に書き留めたのぶは、編集部に戻ってすぐに原稿を仕上げます。
「誤字なし 脱字なし」と自分に言い聞かせる姿には、取材した人たちへの責任感が滲んでいました。
しかし、待っていたのは厳しい現実です。
東海林編集長が「県の没や」と告げたように、せっかくの記事は「勇敢」が発刊できなくなったことでお蔵入りに。
高知県内では土佐新報しか夕刊発刊が認められず、編集部の努力は報われない形となってしまいます。
それでも、のぶは「絶望の隣は希望やって」と仲間たちに言葉をかけ、
編集長の東海林も「上司に説教すんな」と苦笑しつつ、心を救われます。
仲間の辛島や小田たちも、愚痴をこぼしながらも前を向こうとする雰囲気が漂い、
チームとしての結束がこの厳しい局面でも揺らがないことを示していました。
原稿は載らなくても、取材した声は仲間の心を動かし、
次の挑戦への原動力へと変わっていく――それが編集部に残った確かな希望でした。
一県一夕刊の壁と新聞人の誇り
第68話の大きな壁となったのが、「一県一夕刊」の規制です。
戦後の混乱期に、新聞発行の制約として高知では土佐新報だけが夕刊発行を許可されました。
局長の言葉を借りれば「一県につき一朝刊、一県につき一夕刊」という決まりが、
多くの地方紙の夢を押しつぶした形です。
東海林は「夕刊は中止」と部下に告げるしかなく、のぶの努力も形としては残せなくなりました。
しかしそれでも、のぶの「絶望の隣は希望や」という言葉に支えられるように、
新聞人として声を届けることの意味を問い続けます。
これは、高知の小さな新聞社に集う人々が、たとえ規制に阻まれても、
取材の現場で見た真実を諦めずに書き続ける覚悟を示す場面でもありました。
一県一夕刊の壁は大きい――けれど、ペンを置かない限り、彼らの誇りは消えません。
のぶたち新聞人の信念がにじんだ回として、多くの視聴者の心に残る展開となりました。
絶望の隣は希望やの意味とは
第68話で繰り返し語られた「絶望の隣は希望や」という言葉は、物語の軸として強く印象に残りました。
夕刊発刊が中止となり、取材した子どもたちの声も紙面に載せられない現実を前に、編集部の空気は重く沈みます。
そんな中、のぶは「絶望の隣は希望やって。こんなの絶望のうちに入りませんき」と仲間を励ましました。
この言葉は、かつてのぶが誰かに教えられたものであり、今や彼女自身の信念として根付いています。
原稿が没になっても取材で拾った小さな声が消えるわけではなく、必ず次に繋がる――
のぶはその想いを胸に、悲観する仲間に“絶望の中に希望を見つける力”を示しました。
東海林編集長も「上司に説教すんな」と笑いながら、のぶの言葉に救われます。
新聞を届けることができなくても、書くことを諦めない姿勢こそが、新聞人としての誇りであり、
次の可能性を開く小さな希望になるのだと、視聴者に静かに伝えていました。
闇市と『HOPE』雑誌の象徴性
もう一つ、今回のエピソードで印象的だったのが闇市と進駐軍の雑誌『HOPE』の存在です。
高知の闇市で東海林が手にした『HOPE』を、柳井嵩が夢中で読んでいたことが明らかになります。
戦後の混乱の中で、物資が不足し人々が明日の生活さえ不安を抱える状況で、
“HOPE=希望”というタイトルの雑誌を拾い読みする嵩の姿は、若者たちの中に芽生える小さな夢を象徴していました。
この雑誌をきっかけに、辛島健太郎は嵩に廃品の万年筆を誕生日プレゼントとして贈ります。
「雑誌ばっか見とるとらんで、漫画かけばよかろう」という言葉には、
物がなくても、誰かが誰かの背中を押すことで夢が生まれるという希望が込められています。
闇市という混沌とした空間と、英語で“希望”を意味する『HOPE』の対比は、
戦後の街に残る荒廃と、その中で消えずに灯る未来の可能性を示していました。
廃品の万年筆から描き出されるかもしれない嵩の漫画は、のぶの「絶望の隣は希望や」という言葉と響き合い、
エピソード全体を貫く希望の物語を象徴しています。
朝ドラあんぱん第68話 キャラと見どころ

柳井嵩と万年筆のプレゼント
第68話では、柳井嵩が進駐軍の雑誌『HOPE』を夢中で読む姿が印象的に描かれました。
闇市での取材を通して、健太郎は嵩の誕生日を知り、廃品の万年筆を誕生日プレゼントとして渡しました。
「雑誌ばっか見とるとらんで、漫画かけばよかろう」という言葉には、健太郎なりの照れ隠しと、本気で嵩を信じる気持ちが込められています。
「昔みたいにまた絵を描きたい」――嵩の心に眠っていた創作への情熱を、
一番身近な仲間がそっと呼び覚ます。そんな友情の一場面が、万年筆というささやかな贈り物に込められていました。
辛島健太郎の友情と成長
辛島健太郎にとっても今回の誕生日プレゼントのシーンは、彼自身の成長を感じさせる場面でした。
嵩という“仲間”に寄り添い、行動で背中を押す存在へと変わりつつあります。
セリフでも「漫画かけばよかろう」と軽く言っているものの、
廃品の万年筆を自分で探してきてまで渡すその行動には、言葉以上の思いがにじんでいました。
戦後の混乱期という厳しい状況の中で、
一人の若者が誰かの夢を信じ、助けようとする姿は、のぶの「絶望の隣は希望や」という言葉と響き合います。
健太郎の小さな行動が、嵩だけでなく自分自身にとっての“次の希望”になる――
そんな成長の一歩を感じさせる場面でした。
蘭子の夢と家族の支え
第68話のラストでは、のぶの妹・蘭子が見せた小さな夢も心に残りました。
蘭子は姉に「お金を貸してくれ」と頭を下げ、
東京に行きたい理由を「ラジオののど自慢に出たい」と恥ずかしそうに告白します。
「笑われるかもしれん」と言いながらも、「一生のお願いじゃ」と涙ながらに語る蘭子。
この言葉には、戦争で夢を後回しにしてきた若者たちが、もう一度自分の声で未来を切り開こうとする強い意志が込められていました。
のぶは迷わず妹の夢を支えようとし、「どういても必要なお金やったらうちが出すき」と背中を押します。
姉妹の絆、家族の支えが、蘭子の小さな挑戦に希望を与えました。
誰もが声を上げるのをためらった時代だからこそ、
「夢を語る」ことの尊さを改めて感じさせてくれる場面でした。
朝田家の姉妹が語る未来
第68話では、新聞社で奮闘するのぶと、
新しい夢を口にした妹・蘭子の言葉の会話が象徴的でした。
夕刊発刊の中止で落胆する仲間を前に、のぶは「絶望の隣は希望や」と力強く言い切り、
新聞記者として子どもたちの声を残す決意を貫きます。
一方で蘭子は、これまで胸にしまっていた想いをついに打ち明け、
「ラジオののど自慢に出たい」という夢を語りました。
姉は夢を応援し、妹は未来へ一歩踏み出す勇気を得る――
朝田家の姉妹が口にした言葉には、戦後の混乱期においても、
“誰かのために声を届ける”という共通の信念が宿っていました。
姉の言葉と行動が妹の背中を押し、
小さな挑戦が家族の未来をつないでいく――
そんなささやかな希望が、姉妹の絆の中に描かれた回でした。
戦後の街と若者たちの小さな一歩
朝ドラ「あんぱん」第68話は、戦後復興期の高知を舞台に、
荒廃した街で生きる子どもたち、新聞人たち、若者たちが
“声をあげる”ことで希望をつないでいく物語でした。
孤児たちの「元の街に戻りたい」「お父さんを返してほしい」という願い、
編集部員たちの取材と葛藤、そして柳井嵩の万年筆と『HOPE』雑誌――
全てが「絶望の隣に希望がある」という言葉で繋がっています。
健太郎の友情と行動、蘭子の夢と姉の支えは、
どれも派手ではないけれど確かに未来へ続く“小さな一歩”です。
誰もが自分の立場でできることを探し、
夢や言葉を失わずに踏み出す若者たちの姿が、
戦後の街に残されたわずかな光として描かれました。
この物語は、これからどんな希望の種が芽吹くのかを
視聴者にそっと問いかけているかのようです。
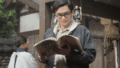

コメント